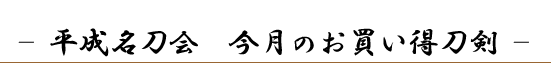
 *画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
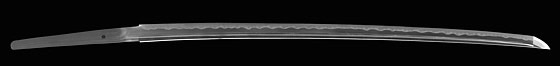 *画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
 *画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
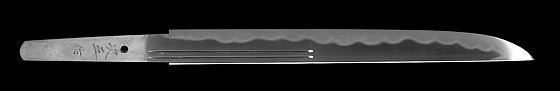 *画像をクリックして頂くと詳細がご覧頂けます。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| このページを閉じる |